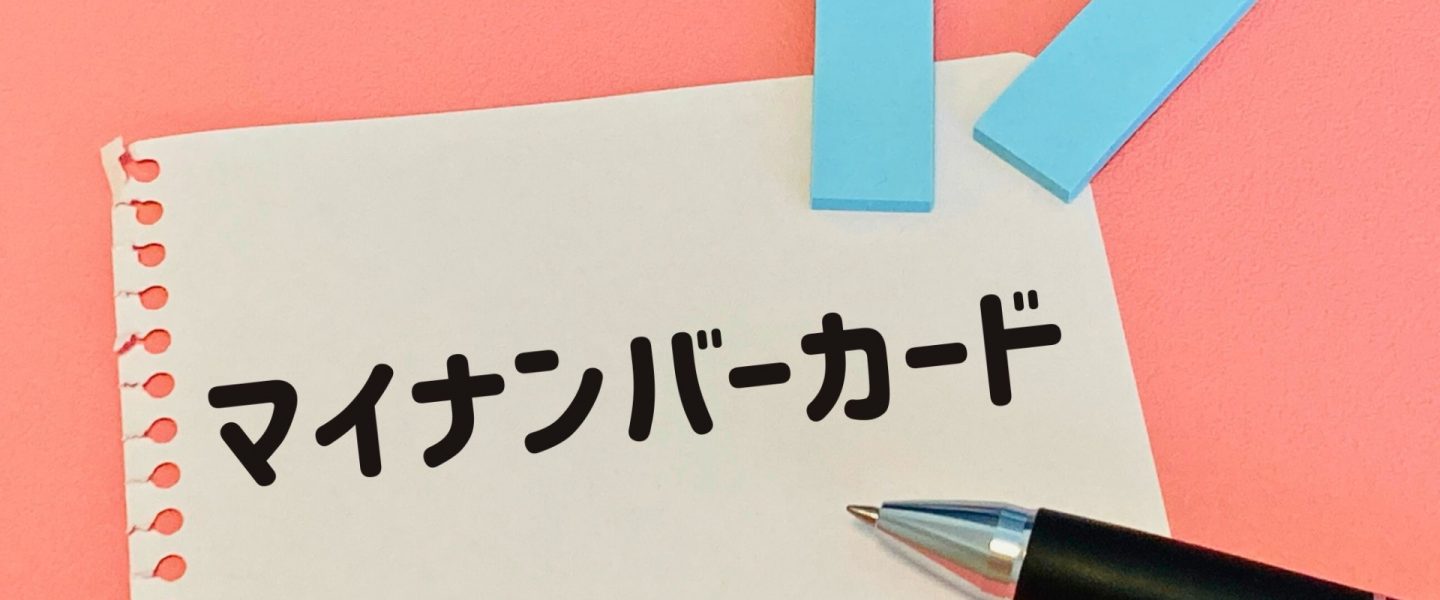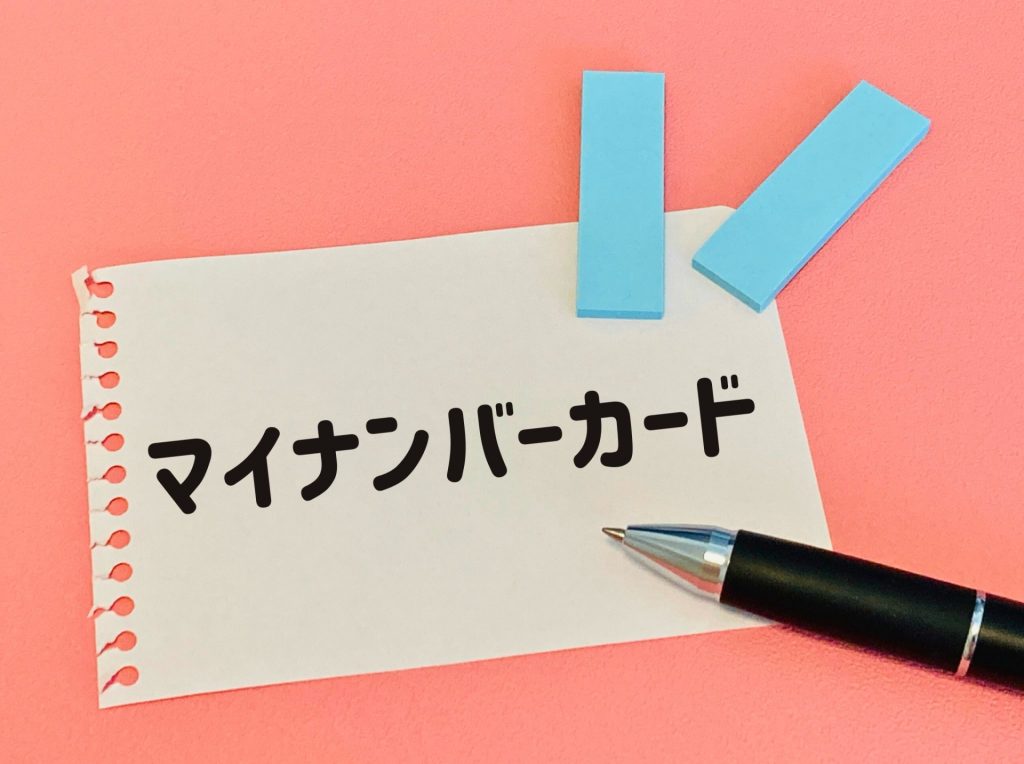
2024年12月より健康保険証の新規発行が停止され、整骨院や接骨院でもマイナンバーカード(通称:マイナ保険証)を用いた「オンライン資格確認」の導入が原則義務化となりました。本記事では、整骨院が対応すべきオンライン資格確認の基本から、導入手順、補助金制度、注意点までを網羅的に解説します。これから導入する方、既に導入済みの方にも役立つ内容です。
マイナンバーカードとマイナ保険証の基礎知識
整骨院においてマイナンバーカードを保険証として活用する仕組みが本格的に導入された今、まずはこの制度の基本を正しく理解することが大切です。
特に、整骨院の現場では「マイナ保険証」に関する誤解や疑問も多いため、制度の成り立ちや運用範囲を知ることがスムーズな対応につながります。
ここでは、「マイナンバーカードとは何か」「マイナ保険証としてどのように使われるのか」「整骨院での活用範囲」について解説します。
マイナンバーカードとは?保険証としての活用方法
マイナンバーカードとは、日本に住民登録のあるすべての人に割り当てられている12桁の個人番号(マイナンバー)と、顔写真・氏名などが記載されたICチップ付きのカードのことを指します。
このカードは本人確認書類としてはもちろん、税や行政手続き、そして医療機関での利用など、幅広い用途で活用できる公的な身分証明書です。
令和3年10月からは、このマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりました。
カード内部のICチップを活用し、専用のリーダー機器で読み取ることで、健康保険の資格確認がオンライン上で自動化されるのです。
従来の保険証では、記載内容の目視確認や有効期限のチェックなどを手作業で行う必要があり、確認ミスや手続きの手間が課題とされてきました。
しかしマイナンバーカードを使えば、以下のようなメリットがあります。
【マイナンバーカードの主な保険証利用メリット】
- 資格情報がリアルタイムで確認できるため、入力ミスや確認漏れを防げる
- 患者側も健康保険証を持ち歩く手間が省ける
- 医療費控除が自動で反映されるようになる
さらに、病院やクリニックではこのカードを通じて過去の診療履歴や処方履歴の共有も可能になっており、医療の質を高めるインフラとして注目されています。
マイナ保険証とは?整骨院での活用可能範囲
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにした新しい保険証のかたちです。
ただし、この制度が整骨院や接骨院で利用可能になったのは、2024年4月からと、医療機関に比べて導入のタイミングが遅れています。
整骨院におけるマイナ保険証の取り扱いには、医療機関とは異なる「資格確認限定型」という特徴があります。
これは、患者の保険資格のみを確認する仕組みであり、病院のように診療情報を共有することはできません。
【整骨院でのマイナ保険証活用範囲】
- オンラインで保険資格の確認が可能
- 医療情報(受診歴・薬歴など)の共有は不可
- 資格確認後は紙の保険証と同様の取扱いが可能
この資格確認限定型の活用により、整骨院では患者が持参したマイナンバーカードをリーダーで読み取ることで、その場で保険資格の有無をチェックできます。
確認作業が効率化されるうえ、保険証の有効期限切れによる誤請求リスクも大幅に軽減されます。
また、整骨院側はマイナ保険証対応をすることで、患者満足度の向上にもつながります。
患者にとっては、1枚のカードで行政・医療サービスが一元化され、手続きの手間が少なくなるためです。
ただし注意点として、整骨院で保険が適用されるのは「外傷性の疾患(例:打撲・捻挫など)」に限られるため、制度の活用にあたっては患者への丁寧な説明も必要となります。
整骨院でのオンライン資格確認の導入方法
整骨院や接骨院において、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の導入が2024年4月から本格的に始まりました。
これにより、保険証の資格確認をシステム化でき、受付業務の効率化や人的ミスの削減が実現可能となります。
導入が義務化されたことで、準備がまだの整骨院は早急な対応が求められています。
ここでは、具体的な導入ステップと必要な機材について詳しく解説します。
【5STEP】導入手順を徹底解説
オンライン資格確認を整骨院で導入するためには、計画的にステップを踏むことが重要です。
以下に、導入に必要な5つのステップを詳しくまとめました。
STEP1:使用端末の選定・購入
オンライン資格確認を行うには、インターネット接続可能な端末が必須です。
パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかを選びましょう。
- NFC対応のスマートフォンやタブレットなら、専用カードリーダーが不要
- パソコン利用時は有線接続の汎用カードリーダーが必要
整骨院の規模や運用体制に合わせて、最適な機材を選定してください。
STEP2:施術所等向け総合ポータルサイトへの登録
機材の準備ができたら、まずは施術所等向け総合ポータルサイトにユーザー登録を行います。
【登録に必要な情報】
- 施術所名と所在地
- 登録記号番号(受領委任承諾通知書に記載)
- 連絡先情報(電話・メールなど)
事前に受領委任の手続きを完了しておくことが前提になります。
STEP3:利用開始申請
ポータルサイトにログインし、「各種申請」メニューからオンライン資格確認の利用開始申請を行います。
入力項目は以下のとおりです。
- 施設確認方法(書類添付または照合)
- 利用職員数
- 利用端末の台数
入力が完了したら、システムに申請を送信し、登録確認メールを受け取ります。
STEP4:マイナ資格確認アプリのダウンロードと初期設定
各端末に「マイナ資格確認アプリ」をインストールします。
Google PlayまたはApp Storeから無料でダウンロード可能です。
初期設定では以下の情報が必要です。
- 機関コード
- ID・パスワード
- アクティベーションコード
登録内容を間違えないように注意しながら設定を進めましょう。
STEP5:運用開始に向けた準備
アプリの動作確認が完了したら、実際に現場での運用シミュレーションを実施します。
患者対応の流れ、本人確認手順、万一のトラブル時対応をスタッフ間で共有しておくことが大切です。
オンライン資格確認に必要な機材と対応機種
導入にあたっては、端末やカードリーダーなどの機材選びも非常に重要です。
整骨院の運営スタイルに合ったものを選ぶことで、スムーズな導入と運用が可能になります。
【機材一覧とその特徴】
| 機材名 | 特徴・用途 | 補助金対象 |
| 汎用カードリーダー | PC・タブレットと接続してカードを読み取る | 対象 |
| NFC対応スマートフォン | 単体でICチップ読み取り可能 | 対象 |
| NFC対応タブレット | スマホと同様の用途で、画面が大きく使いやすい | 対象 |
対応端末の選び方のポイント
- 訪問施術中心の院はスマートフォンが最適
- 院内運用が中心ならPC+カードリーダーが安定
- スタッフのITスキルや設置スペースも考慮
また、古い端末ではアプリが正常に動作しない場合があります。
最新OSや拡張APDU(Lc/Le)対応端末かどうかを事前に確認しましょう。
その他に必要なもの
- 安定したインターネット回線(Wi-Fi推奨)
- 設置スペースや患者のプライバシーに配慮した端末配置
- セキュリティ対策済みのOS・セキュリティソフトの導入
導入後のトラブルを避けるためにも、必要な機材は早めに準備しておくことをおすすめします。
導入時に使える補助金・支援制度
整骨院でオンライン資格確認を導入する際には、初期費用や機材購入の負担が気になるという声も多く聞かれます。
しかし実際には、国からの補助金制度を活用することで、負担を大幅に軽減することが可能です。
この章では、補助金の内容や申請方法、今後の支援の見通しまでを詳しく解説していきます。
最大41,000円の補助!申請方法と必要書類
オンライン資格確認を導入する整骨院・接骨院を対象に、最大41,000円の補助金が支給されます。
この制度は、厚生労働省が整備を進める「資格確認システム普及施策」の一環であり、要件を満たすすべての施術所に利用可能です。
補助対象となる費用
以下のような導入機材や通信端末の購入費用が補助の対象になります。
【補助対象機器の例】
- 汎用カードリーダー(有線・無線)
- NFC対応スマートフォン
- タブレット端末
- インターネット環境構築にかかる初期機材
これらは、いずれも患者のマイナンバーカード情報を読み取るために必要な機器です。
補助金の申請手順
補助金の申請は、「施術所等向け総合ポータルサイト」からオンラインで手続きを行います。
以下のようなステップで申請を進めてください。
【申請の流れ】
- 総合ポータルサイトにログイン
- 「各種申請」メニューから補助金申請を選択
- 対象機器の情報・購入日・金額を入力
- 必要書類をアップロード
- 内容を確認して申請を送信
提出後、審査を経て補助金が指定口座へ振り込まれる流れとなります。
提出が必要な書類一覧
補助金を申請する際には、以下の書類が必須となります。
- 領収書(原本のコピー)
- 領収書の内訳書
- 口座情報が確認できる通帳の写し
- オンライン資格確認等事業完了報告書
※書類の不備があると、申請が無効になる可能性があるため、内容の正確性をしっかり確認しましょう。
今後の追加補助の可能性と注意点
現行の補助金制度に加えて、今後はさらに追加支援が行われる見込みもあります。
令和6年度補正予算案では、整骨院や接骨院などの「あはき・柔整療養費関連施術所」への新たな協力金の支給が盛り込まれました。
今後予定されている追加補助の内容
以下のような支援が検討・計上されています。
| 補助名称 | 支給内容 | 支給時期(予定) |
| マイナ保険証導入協力金 | 1院あたり5万円 | 令和7年3月〜4月頃 |
| 療養費制度見直し調査費 | 約2,700万円(全体予算) | – |
これらは、厚生労働省が主体となって進めている施策で、国全体としてオンライン資格確認の普及を強力に後押ししています。
申請時の注意点
補助金を受け取るには、いくつかの重要な条件や注意点があります。
- 補助金の申請は1回限り。再申請は不可
- 申請期限(例:2025年2月1日など)を過ぎると受付不可
- 対象機材であっても、領収書が不備だと無効
また、施術所の中には「高齢施術者のみ」や「年内に廃業予定」などの理由で義務化対象外となるケースもあるため、該当するかどうかを必ず確認しましょう。
補助制度は継続か、終了か?
2025年度以降も同様の補助制度が継続されるかどうかは、現時点では未定です。
そのため、導入を検討している整骨院は、今の補助制度が活用できるうちに申請することが賢明です。
補助金や支援制度をうまく活用すれば、整骨院におけるオンライン資格確認の導入コストを実質0円に抑えることも可能です。
制度の詳細をしっかり把握し、早めの申請でスムーズな導入を実現しましょう。
マイナ保険証導入における注意点とトラブル対策
マイナ保険証によるオンライン資格確認を導入することで、整骨院の業務は大幅に効率化され、患者の利便性向上にもつながります。
しかしその一方で、運用の不備やトラブルの発生リスクも無視できません。
実際の運用現場では、患者対応時の混乱や個人情報の管理不足が信頼性の低下やクレームの原因になることもあります。
ここでは、トラブルを防ぐために重要な注意点と具体的な対策を詳しく解説します。
患者対応時の注意点と院内フローの構築
オンライン資格確認をスムーズに行うためには、患者対応時の流れを明確に定めておくことが重要です。
特に初めてマイナ保険証を使う患者には、丁寧でわかりやすい案内が求められます。
よくあるトラブルとその予防策
マイナ保険証の導入初期には、以下のようなトラブルが頻発しています。
【患者対応時の主なトラブル】
- 「マイナ保険証を持っているが使えなかった」
- 「顔認証や暗証番号で認証エラーが出た」
- 「従来の保険証を持参していないため受付できなかった」
これらの問題を防ぐには、あらかじめ患者に利用方法を説明し、必要に応じて保険証の併用を促す対応が有効です。
スムーズな院内オペレーションを実現するには?
スタッフ全員が統一されたフローで対応できるように、マニュアルの整備とロールプレイを実施しましょう。
以下のような院内オペレーションを整えることで、現場の混乱を最小限に抑えることができます。
【おすすめの患者対応フロー】
- 来院時にマイナンバーカードの有無を確認
- 利用意思の有無をヒアリングし、説明を行う
- 顔認証 or 暗証番号入力による本人確認を実施
- 認証エラー時は保険証提示を案内し代替対応
- 確認結果をレセプト記録・施術前確認に反映
患者への声かけや案内文も事前に準備しておくと、現場対応がよりスムーズになります。
個人情報保護とセキュリティ対策の必要性
マイナ保険証の導入により、患者の保険情報や個人情報をデジタルで扱う機会が増加します。
それにともない、整骨院にはより高いセキュリティ意識と具体的な対策が求められます。
なぜセキュリティ対策が必要なのか?
マイナンバーカードは、国が発行する重要な個人識別情報を含んだカードです。
読み取り時にアクセスする保険情報には、氏名・生年月日・保険者番号など個人特定が容易なデータが含まれており、流出時のリスクが極めて高いと言えます。
情報漏洩は信頼の失墜につながり、法的責任が問われる可能性もあるため、以下のような基本対策が不可欠です。
セキュリティ対策の基本と推奨事項
【整骨院で実施すべきセキュリティ対策】
- 端末にウイルス対策ソフトを導入する
- Wi-Fiや通信機器にパスワードロックをかける
- カードリーダーやスマートフォンを無人の状態で放置しない
- マイナンバー対応端末は業務専用とし、私的利用を避ける
- 操作ログや通信履歴を定期的にチェックする
また、患者のカードを読み取る場所も配慮が必要です。
たとえば受付カウンターに仕切りを設置するなどの物理的対策により、他の患者から情報が見えない工夫も求められます。
スタッフ教育も不可欠
システムや設備だけでなく、実際に操作するスタッフの意識と知識も極めて重要です。
定期的に研修を行い、セキュリティの基礎知識や具体的な対応フローを全員が共有できるようにしましょう。
「何が個人情報か」「どの操作が危険か」という観点をもつことで、未然にトラブルを防ぐ環境を構築できます。
マイナ保険証の運用には、患者対応と情報管理の両面での準備が欠かせません。
適切なフローの整備とスタッフの教育、そして機器やシステムのセキュリティ強化によって、安全で信頼性の高い運用を実現しましょう。
まとめ
マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認の導入は、整骨院にとってこれからの運営に欠かせないインフラ整備のひとつです。
患者の利便性を高め、保険確認業務の負担を軽減できるこの制度を、いち早く取り入れることが安定した経営基盤を築く第一歩となります。
これから開業を目指す整骨院にとって、信頼される院づくりに必要な要素のひとつが「正確な情報管理とスムーズな受付体制」です。
さらに、開業直後から成果を出すためには、効率的な集患体制や導入機器の選定も成功のカギとなります。
そこで私たち武蔵野メディカルシステムでは、全国1,000院以上のサポート実績と、上位3%の繁盛院から得た成功パターンをもとに、整骨院の成長をトータルで支援しています。
現在おすすめしているのが、施術者の時間と負担を大幅に軽減し、患者満足度の向上にもつながる直流微弱電流治療器【時短君】®です。
【時短君が選ばれる理由】
- わずか数秒から長くても5分程度で除痛効果、可動域改善、浮腫軽減が見込めます。
- 施術スタッフの時間と手間を削減できる省人化設計
- 導入初月から月商アップを実現した成功事例が多数
機器導入をご検討中の方や、整骨院開業で「何を選べばいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。
Zoomを活用したオンライン説明会も随時開催中です。
地域の患者様に選ばれる整骨院づくりを、一緒に実現していきましょう。