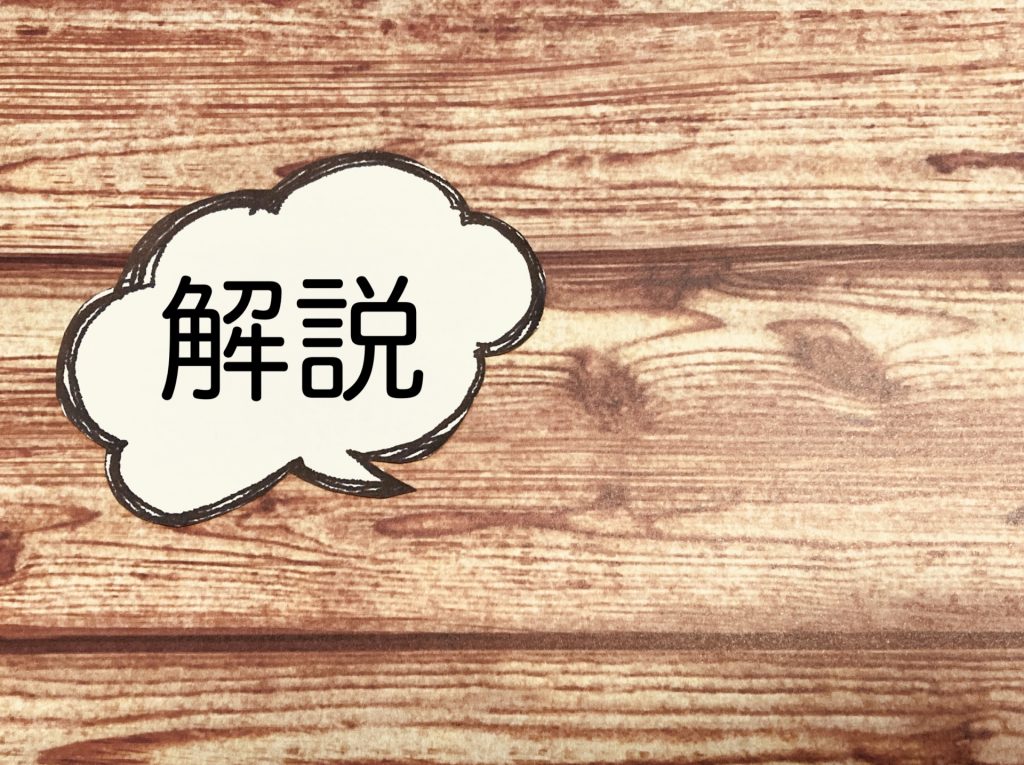
柔道整復師として整骨院や接骨院を開業すると、施術そのものだけでなく**「レセプト業務」が経営の大きな柱となります。
レセプトは保険請求を行うために必要な書類であり、内容に不備があれば返戻や支払い遅延**といった経営リスクに直結します。
特に、開業直後は「どの手続きから始めれば良いのか」「算定のルールをどう理解すべきか」と迷う場面が多いものです。
さらに、算定基準は複雑であり、初検料や再検料、骨折・脱臼の特別な算定ルールまで把握しなければなりません。
本記事では、柔道整復師が押さえておくべきレセプト業務の全体像をわかりやすく整理しました。
準備から算定基準、作成手順、返戻防止策まで順を追って解説しますので、これから請求業務を始める方も、すでに取り組んでいる方も参考になるはずです。
レセプト作成の前に必要な準備

受領委任契約とその手続き
柔道整復師が保険請求を行うには、まず**「受領委任契約」**を締結する必要があります。
受領委任契約とは、患者が治療費を一旦全額支払うのではなく、柔道整復師が直接保険者に請求できる仕組みを指します。
契約の手続き方法は大きく2つに分かれます。
1つ目は、公益社団法人である柔道整復師会に加入して契約を結ぶ方法です。
この場合、必要書類や流れについてサポートが受けられるため、初めて請求を行う人にとって安心です。
2つ目は、柔道整復師団体に所属しない場合に地方厚生局や都道府県知事と直接契約を行う方法です。
この場合は自分で情報収集を行い、正しい届け出を提出する必要があります。
受領委任契約を結ばなければ、保険を用いた施術は請求できません。
そのため、開業前に確実に契約を終えておくことが重要です。
各管轄への届出と承諾通知書の確認
受領委任契約を済ませた後は、各管轄への届出を行います。
管轄には以下のような種類があります。
- 地方厚生局
- 共済組合(公務員の健康保険を扱う)
- 防衛省(自衛官の健康保険を扱う)
- 労災指定(労災保険の対象)
- 生活保護指定(生活保護受給者の取扱い)
これらの届出が受理されると、承諾通知書が発行されます。
この通知書の日付以降から、正式に受領委任払いでの保険請求が可能になります。
届出や承諾通知の確認を怠ると、正しく請求しても無効扱いになる可能性があるため注意が必要です。
必ず承諾日を確認し、カルテやレセプトに記録しておくことが大切です。
柔道整復師のレセプト算定基準

初回施術で算定できる項目(初検料・相談支援料など)
初めて来院した患者に対しては、**「初検料」**を算定できます。
これは施術部位が複数あっても1回のみであり、同じ部位を1か月以上空けて再び施術した場合は再度算定が可能です。
また、初回の診療時に生活習慣やスポーツ活動での注意点を丁寧に説明した場合は**「初検時相談支援料」**が算定できます。
これは「日常生活での指導をどれだけ具体的に行ったか」がポイントです。
さらに、診療時間外や深夜に施術した場合は時間外加算や深夜加算が認められます。
ただし、通常診療時間として設定している場合は加算対象外になるため注意が必要です。
初回施術での算定はその後のレセプト全体に影響するため、適切な判断と記録が欠かせません。
2回目以降に算定できる項目(往療料・罨法料・電療料など)
2回目以降の施術では、患者の状態や施術内容に応じて以下の算定が可能です。
- 往療料:歩行困難や絶対安静の患者宅に訪問した場合に算定。16km以上の往療は対象外。
- 罨法料:冷罨法や温罨法を用いた施術。ただし、受傷からの日数によって算定不可の場合あり。
- 電療料:低周波や超音波などの電気療法を併用した場合に算定可能。
また、再検料は初検後の最初の後療日に1回だけ算定できます。
これは「今後の施術が必要かどうかを判断する検査」と位置づけられています。
これらの算定項目を正しく適用しなければ、返戻や減額につながるリスクが高まります。
骨折・脱臼の算定と金属副子等加算
骨折や脱臼の場合は、算定ルールがさらに複雑になります。
- 肋骨骨折は左右単位で算定
- 手指や足趾の骨折は1本単位で算定
- 頭蓋骨や脊椎など一部の骨折は原則算定不可(ただし医師依頼時は可)
固定に使用する金属副子や合成樹脂副木などは、「金属副子等加算」として別途算定可能です。
ただし、交換できる回数は2回までと制限があります。
摘要欄に使用日や医師依頼の有無を必ず記載することが、返戻防止のカギとなります。
その他の算定ルール(近接部位・3部位以上の施術など)
その他の算定基準として代表的なのは、近接部位の扱いと3部位以上の施術制限です。
- 近接部位:肩と上腕など、解剖学的に近い部位は別部位として算定できない場合があります。
- 3部位以上の施術:3部位目までは算定できるが、4部位目以降は対象外。さらに、3部位目の後療料などは60%相当額で算定。
このように、算定ルールは例外や制限が多いため、常に厚生局の最新資料を確認する必要があります。
レセプト作成の手順と注意点

レセコン入力から電子レセプト作成までの流れ
レセプト作成は以下の流れで進みます。
- レセコンへ診療情報を入力
診療内容コードや使用した医療器具の情報を入力します。 - 電子レセプトを作成
入力が終わるとレセコンが自動的に診療報酬額を計算し、月ごとのレセプトを生成します。 - 点検と修正
入力ミスや算定漏れがないかを必ず確認します。 - 提出
支払基金や国保連合会へ提出。郵送や電子データ送信が一般的です。
この流れの中で特に重要なのは、点検作業をどれだけ丁寧に行うかという点です。
返戻を防ぐための点検と確認作業
返戻の主な原因は、保険証番号や氏名、生年月日の誤記載など基本情報のミスです。
さらに、算定ルールを無視した請求や、摘要欄への記載漏れも大きな要因です。
返戻を防ぐには以下のチェックが有効です。
- 保険証情報をコピーではなく原本を確認する
- 算定基準を一覧表にして施術ごとにチェックする
- 摘要欄記載ルールをスタッフ全員で共有する
返戻は経営に直接響くため、事前の点検こそ最も重要な作業と言えます。
医師同意や長期理由などの記載ルール
骨折や脱臼に関しては、応急処置以外の施術には医師の同意が必須です。
その日付をカルテとレセプト双方に明記しなければなりません。
また、捻挫や打撲などが3か月を超えて長期施術となる場合は、**「長期施術継続理由書」**を添付する必要があります。
この添付がないと、請求が否認される可能性が高くなります。
記載ルールを徹底することで、返戻や減額を未然に防ぐことが可能です。
返戻・再請求が経営に与える影響
返戻が発生すると、再請求までに1か月以上の支払い遅延が発生します。
これはキャッシュフローを圧迫し、スタッフ給与や家賃の支払いに影響を及ぼす恐れがあります。
さらに、返戻率が高い施術所は保険者からの信用低下にもつながります。
信用が下がれば、今後の請求審査がより厳格になり、経営の安定性を損ないます。
そのため、柔道整復師にとって返戻対策は**「単なる事務作業」ではなく「経営戦略の一部」**と捉えるべきです。
まとめ

柔道整復師にとってレセプト業務は単なる事務処理ではなく、経営を安定させるための最重要業務です。
受領委任契約の手続きや各管轄への届出、算定基準の理解、レセコンを活用した正確なレセプト作成など、一つひとつの流れを丁寧に行うことで返戻リスクを最小限に抑え、安定した収益を確保することができます。
また、算定基準は頻繁に改定されるため、常に最新情報を確認し、医師同意や長期施術理由書といった記載ルールを徹底することが信頼される施術所の条件となります。
返戻が発生すれば、再請求による入金遅延や経営への悪影響は避けられません。
そのため、正確なレセプト作成は院の存続にも直結する経営課題だと言えるでしょう。
さらに、整骨院経営では効率化と差別化も重要なテーマです。
患者様の満足度を高めるだけでなく、スタッフの負担軽減や売上向上に直結する施術機器の導入も欠かせません。
その中でも注目されているのが、武蔵野メディカルシステムが提供する**次世代EMS「時短君」**です。
【時短君が選ばれる3つの理由】
- わずか30分で深層筋にアプローチできる高出力EMS
- 施術スタッフの負担を軽減する省人化設計
- 導入初月から月商アップの成功事例が多数
柔道整復師にとって、レセプト業務の効率化と施術の質の向上は両立すべき課題です。
その両方をサポートできるのが、武蔵野メディカルシステムの豊富な整骨院支援ノウハウと、次世代EMS「時短君」の活用です。
「どのEMSを導入すべきか迷っている」
「効率的に院の売上を伸ばしたい」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談やZoom説明会をご利用ください。
👉 整骨院開業・経営支援のお問い合わせはこちら
👉 時短君(次世代EMS)製品ページはこちら
柔道整復師としての専門性を活かしながら、患者様に選ばれる整骨院経営を一緒に築いていきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現場で1分の変化を体感できる
直流微弱電流治療器【時短君】®
施術時間短縮・回転率向上・患者満足度アップを 目指す先生へ、無料デモをご案内しています。
▶ 無料デモ申し込みはこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
