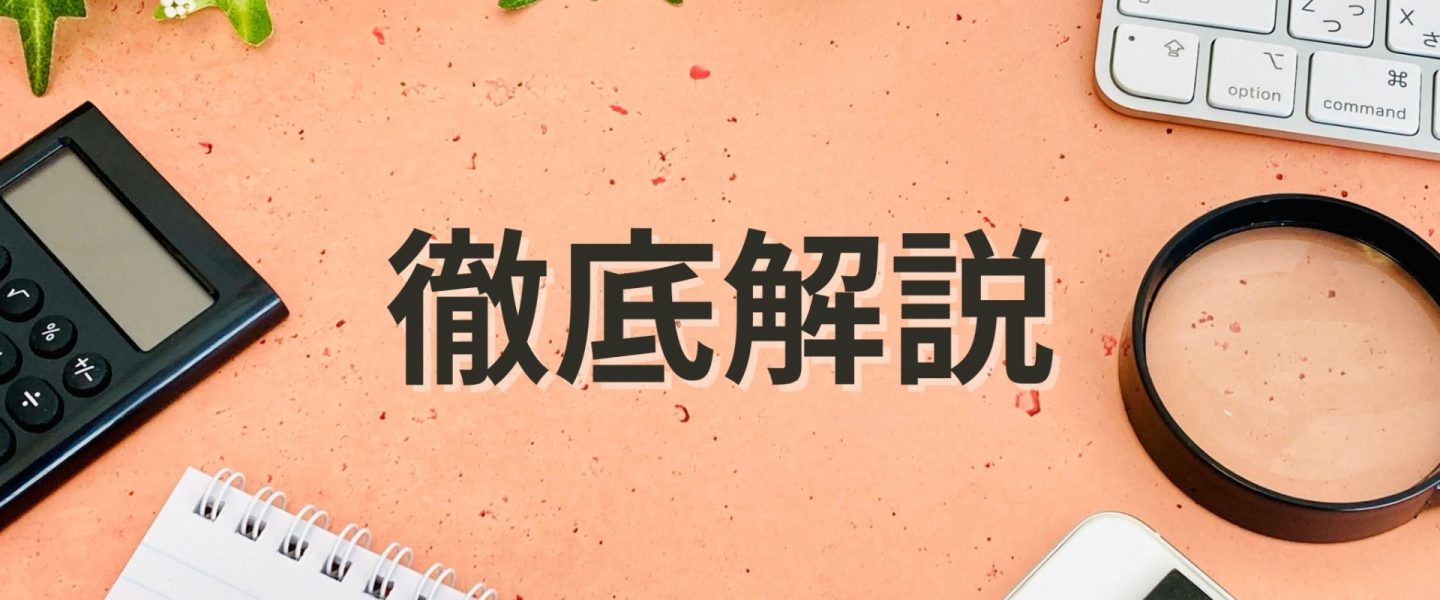整骨院の数はここ20年ほどで大きな変化を遂げてきました。
規制緩和をきっかけに急増した整骨院数は、一時期は順調に拡大を続けましたが、近年では伸びが鈍化し、業界全体の課題が浮き彫りになっています。
読者の多くは「整骨院の数は今後どうなるのか」「業界の成長は続くのか」といった疑問を抱いていることでしょう。
実際に、高齢化による需要の増加や同業・異業種との競争激化、さらに保険制度の見直しなど、複数の要因が複雑に絡み合い、整骨院業界は転換期を迎えています。
本記事では、整骨院数の推移をデータに基づいて解説し、その背景にある制度や社会的要因を整理します。
また、現在の厳しい経営環境や不正請求問題などの現状に触れ、今後の展望についても具体的に紹介します。
「整骨院数 推移」というキーワードから業界の流れを理解することで、今後のビジネスチャンスや課題を読み解くヒントが得られるはずです。
整骨院数の推移と背景

規制緩和による整骨院の急増
整骨院数の推移を語る上で欠かせないのが、1998年に実施された柔道整復師養成施設の規制緩和です。
この制度変更により新たな養成学校が次々と設立され、資格取得者が急速に増加しました。
結果として整骨院の開業が全国に広がり、2000年代以降は右肩上がりの成長を続けました。
2008年には全国で34,839件と報告され、その後も増加は続きました。
以下のように、整骨院数の急増が確認できます。
| 年度 | 全国の整骨院数 |
| 2000年 | 約25,000件 |
| 2008年 | 34,839件 |
| 2018年 | 50,077件 |
整骨院の数が増えた背景には、高齢化の進展による慢性的な痛みのニーズや、国家資格としての安定した就職先の魅力もありました。
一方で、供給過多が徐々に業界全体の課題へとつながっていきます。
近年の整骨院数の変化と停滞傾向
2010年代以降も整骨院数は増加を続けましたが、近年は成長が鈍化し停滞の傾向が見られます。
厚生労働省の報告によれば、2018年の50,077件をピークに、伸び率は低下していることが分かります。
背景には以下の要因があります。
- 新規参入が一巡し、開業ペースが落ち着いた
- 同業種間の競争激化により廃業が増加した
- 保険制度の厳格化で採算性が低下した
特に2020年以降はコロナ禍の影響もあり、患者数の減少や経営難による閉院が目立ちました。
供給過多と需要の伸び悩みが並行して進んだことで、かつての急増時代からは明らかに転換期を迎えています。
整骨院業界を取り巻く現状

競争激化と市場規模の縮小
整骨院数の推移が示すように、全国的な増加は業界全体に過剰な競争環境を生み出しました。
同業の整骨院だけでなく、整体院・リラクゼーションサロン・整形外科などとの顧客争奪が激化しています。
市場規模を見ても、矢野経済研究所の調査では、柔道整復・鍼灸・マッサージ市場は2020年時点で縮小傾向にあります。
患者の選択肢が広がる中、整骨院単独での差別化は難しくなっています。
代表的な課題は以下の通りです。
- 保険診療に依存した収益モデルの限界
- 自費診療に切り替える際の集客難
- 地域内の過当競争による利益率の低下
このように、整骨院業界は数が増えたからこそ苦しい時代に直面しているのです。
不正請求問題と規制強化の影響
整骨院業界では、過去に療養費の不正請求問題が大きな社会問題となりました。
例えば、慢性痛や美容目的の施術を「捻挫」などに偽装し、本来は保険適用外の施術を保険請求する事例が相次ぎました。
この問題を受けて、行政は審査体制を強化し、請求手続きの厳格化を進めました。
その結果、療養費の総額は2011年度の4,127億円から2021年度には約4,012億円に減少しました。
規制強化により業界全体の透明性は高まりましたが、同時に経営環境は厳しさを増しました。
特に小規模な整骨院にとっては、保険収入の減少が経営の打撃となり、廃業や倒産に直結するケースも増えています。
今後の整骨院業界の展望

M&Aによる再編と生き残り戦略
近年、整骨院業界ではM&Aによる再編の動きが活発化しています。
大手グループや資本力のある企業が地域の中小整骨院を買収し、店舗網の拡大や経営効率化を図る事例が増えています。
代表例として、全国展開するGENKIDOやケイズグループが挙げられます。
彼らは地域密着型の整骨院を取り込みながら、保険外サービスやトレーナー事業などにも事業を広げています。
M&Aのメリットは以下の通りです。
- 経営資源をまとめ、コスト削減を実現できる
- ブランド力を高めて患者の信頼を得やすい
- 新規事業への投資リスクを抑えられる
今後は単独経営だけでなく、グループ化や提携による業界再編がますます進むと予想されます。
自費診療や異業種連携の広がり
将来の整骨院経営において注目されるのが、自費診療の拡充と異業種連携です。
保険診療だけに頼る経営は限界があり、自由診療メニューの導入が差別化の鍵となります。
例えば、以下のようなサービスが注目されています。
- 美容鍼や骨盤矯正などの健康美容サービス
- アスリート向けのトレーナー事業
- フィットネスジムやリラクゼーションとの複合施設
また、ITやIoTを活用した健康管理サービスとの連携も広がっています。
ウェアラブル端末での体調データ管理や、オンライン相談サービスとの統合など、従来の整骨院の枠を超えた取り組みが進んでいます。
このように、整骨院数の推移が示す停滞期を乗り越えるには、柔軟な発想と新しいビジネスモデルの構築が欠かせません。
まとめ

これまで整骨院数の推移を見てきましたが、規制緩和による急増から始まり、近年の停滞傾向、そして競争激化による経営環境の厳しさまで、業界の大きな変化が浮き彫りになりました。
現在の整骨院経営は、単に施術を提供するだけでは安定が難しくなっています。
保険依存型から自費診療や新しいサービスへの転換、そして効率的な経営戦略の導入が求められています。
その解決策のひとつとして注目されているのが、医療用EMS機器の導入です。
特に武蔵野メディカルシステムが提供する次世代EMS「時短君」は、整骨院の施術の幅を広げながら、経営の効率化にも大きく貢献しています。
【時短君が選ばれる3つの理由】
- わずか30分で深層筋へアプローチできる高出力EMS
- 施術スタッフの負担を軽減する省人化設計
- 導入初月から月商アップの成功事例が多数
整骨院数が増えた今だからこそ、差別化できる施術メニューの導入が必須です。
「どのEMSを導入すべきか迷っている」「効率良く院の売上を伸ばしたい」そんな方は、ぜひ一度相談してみてください。
👉 整骨院開業支援のお問い合わせはこちら(武蔵野メディカルシステム)
👉 次世代EMS『時短君』の詳細はこちら
整骨院の未来を切り拓くのは、正しい経営判断と確かな設備投資です。
今こそ行動を起こし、理想の整骨院づくりを進めていきましょう。